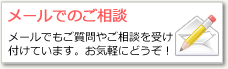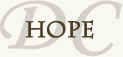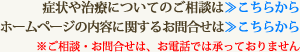


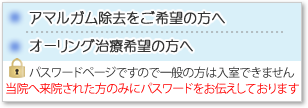
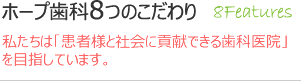
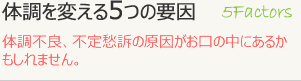
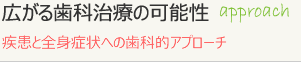
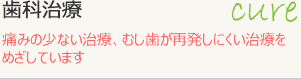
住所
新潟県十日町市寿町2-6-25
アクセスマップ・地図
広い駐車場があります
最寄駅
十日町駅徒歩10分(東口からタクシー3分)
【東京駅から】越後湯沢駅で「ほくほく線」に乗り換え十日町駅下車
TEL
025-752-0525
※12時30分~14時30分の間は、留守番電話に切り替わります。
-----------------
●症状・治療のご相談はこちらから
※お電話では承っておりません
●ホームページの内容に関するお問合せはこちらから
※お電話では承っておりません
診療日時
月曜~金曜 9:00~12:30
14:30~18:30
※12時30分~14時30分の間は、お電話・ご来院とも対応できません。
コンサルテーション(治療説明)及びオーリングによる検査・治療は 12:30~と18:30~となります。
水曜午後・土曜午前は不定期診療です。お問合せ下さい。
休診日
土曜午後・日曜・祝日 ※水曜午後は不定期休診
虫歯治療|歯周病治療|虫歯予防|矯正歯科| 審美歯科|ホワイトニング|顎関節症治療|睡眠時無呼吸症候群の治療|歯科金属アレルギー
|プライバシーポリシー|
Copyright(C) ホープ歯科クリニック All rights reserved.